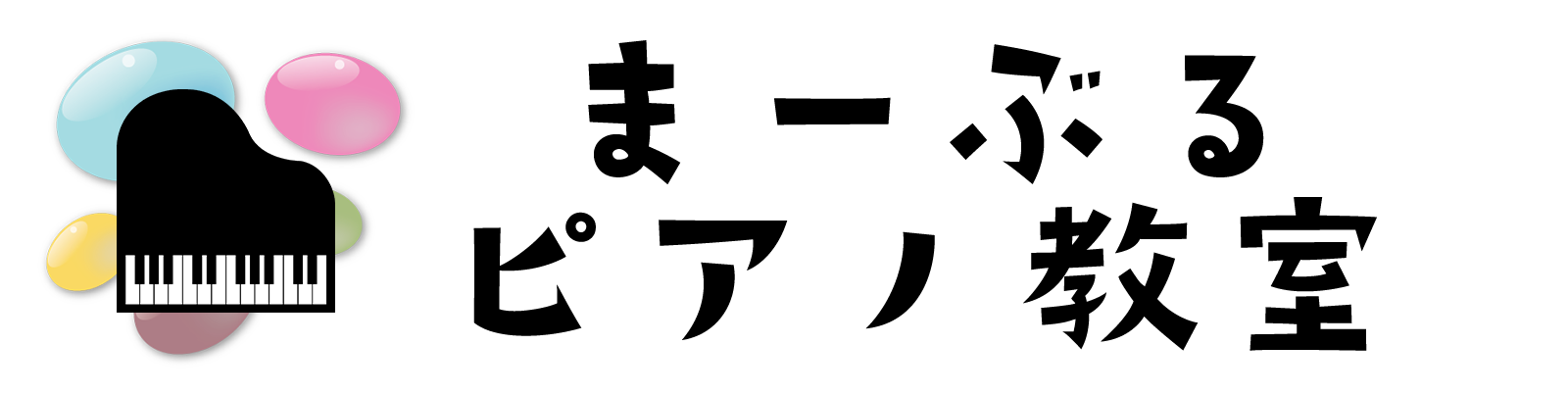読譜の進め方~ピアノ導入期~
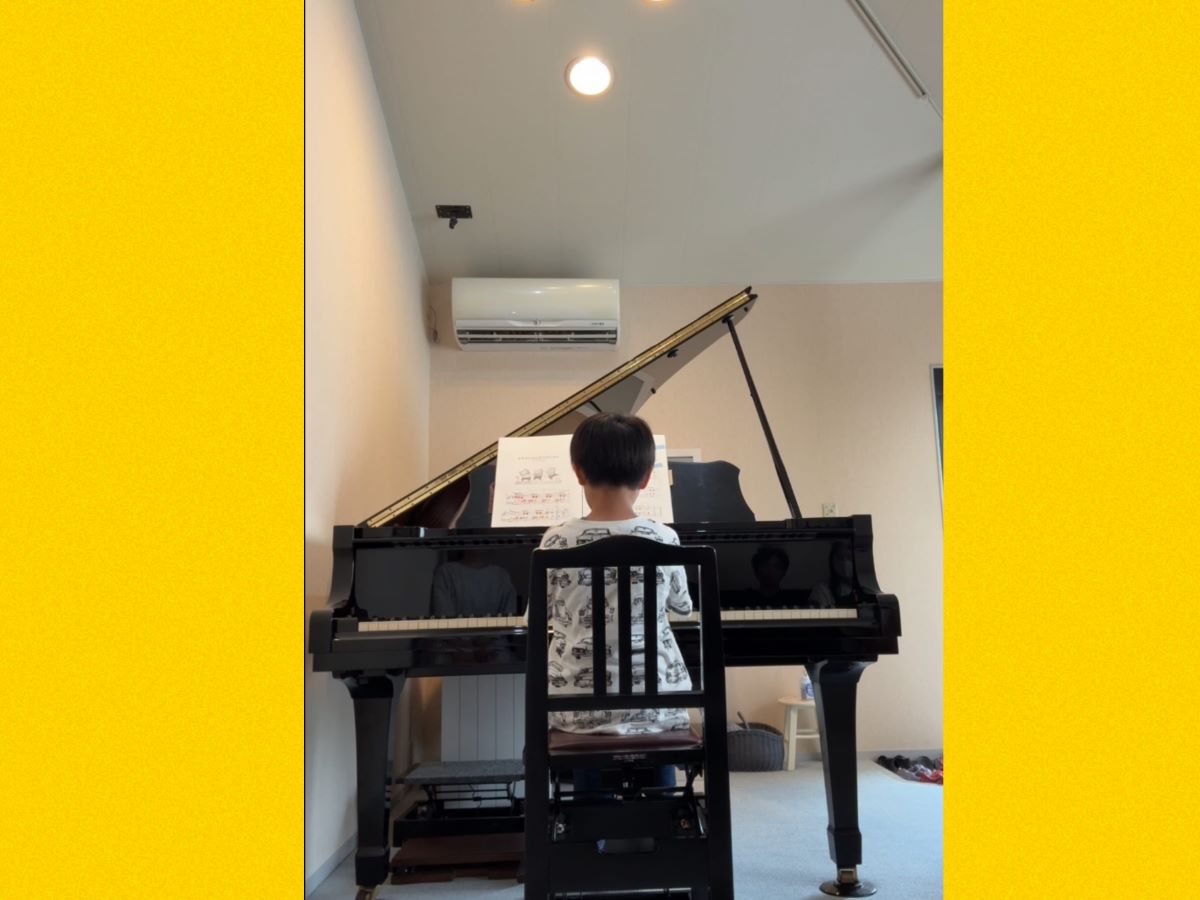
こんにちは♪
金沢市泉野町のまーぶるピアノ教室の
中村真里です。
今日は「ピアノ導入期の読譜の進め方」について
書いてみたいと思います。
♪♪♪
ピアノは88鍵あり、大変音域の広い楽器です。
一般的に使用される楽譜は
大譜表とよばれ、
ト音記号とヘ音記号で書かれています。
ト音記号とヘ音記号
左手と右手の役割分担
✦ト音記号(上段)
右手で演奏する高音部
✦ヘ音記号(下段)
左手で演奏する低音部
この分け方により、演奏者は直感的に
「上の段は右手、下の段は左手」と理解できます。
音楽理論的な意味
ト音記号の「ト」は音名の「G」を
ヘ音記号の「ヘ」は音名の「F」を指しています。
記号の形もそれぞれGとFの位置を
示しています。
大譜表を読むときの注意点
1. 中央ドの位置を覚える
大譜表で最も重要なのは「真ん中のド」の位置です。
この音は…
✦ト音記号では第1加線(五線の下の線)
✦ヘ音記号では第1加線(五線の上の線)
真ん中のドを基準にして
上下の音を読む習慣をつけていきます。
加線に注意
五線を超えた音符は加線で表現されます。
線と間のパターンとして認識したり、
音程や度数の間隔を身に付けると
ラクに読めるようになります。
子供が読譜を習得するために大切なこと
1. 段階的な導入
当教室では以下の通り進めています。
①リズムカード&リズム打ち
最初に4分音符、4分休符を覚えます。
次に4分休符による4拍子、3拍子を打楽器で
鳴らせるようにします。
②弾いてみる
打楽器で鳴らしたリズムを使った
「ド」だけでの曲を弾いてみます。
ト音記号(右手)から始めて、
ヘ音記号(左手)を加えます。
その後、右手のレ、左手のシを加え、
一音ずつ増やしていきます。
2. 視覚的な工夫
✦色分け
左右の手があやふやな場合は、
右手の「ド」は赤、
左手の「ド」は青など、
色分けすると弾きやすくなります。
3. 楽しく継続する工夫
テキストにそったワークを使用して、
ドは赤、レは黄色…などの色塗りをしたり、
五線に〇を書き入れることを続けていると
自分が書いた〇が、
テキストのドレミと同じであることが
わかるようになります。
右手のドレミと左手のドシラが分かると
その先は線と間の関係で
自分で読めるようになる子もいます。
ですが、音が増えてくると
似たような形の音符が出てきて混乱したり、
読めていた音が読めなくなったりすることも
あります…(^-^;
そこで、当教室では
確実に読譜力をつけるために…
〇曲を弾きながら音名で歌う
〇音階ボードに音符を並べる
〇ビッツメロディ(音符カード)
〇ワーク
〇五線紙に音階を書く
などを
確実に読めるようになるまで続けます (*^^*)
♪♪♪
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました ヽ(^o^)丿